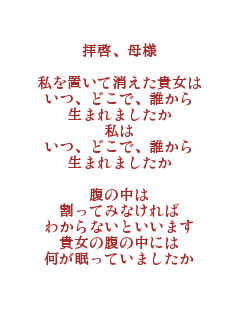book
□姑獲鳥
1ページ/1ページ
私の母は人攫いでございました。
ええ、もちろん貴方の思う通りの人攫いです。
母はかつて、夫との間にできた第一子を流産したのです。子どもができることすら奇跡だと言われますので、特に珍しいものではないでしょう。いえ、そもそもが不気味な事象だと思うのです。女の腹の中で、その血肉を奪って赤子は育ちます。おぞましいことではありませんか。肉の糸を繋ぎ、ただの肉塊は人型を得るのです。羊水という海を用意させ、十月十日の間そこで眠り、外界とは肉の壁を隔てて生きています。
ならば母親とは、浅ましい生き物です。
そうして赤子が育つにつれ大きく膨らんでいく腹を、彼女たちは愛おしそうに見詰めるのですから。気味が悪いとは思わないのでしょうか。あの中で、人間のふりをしたものが人間になるのを待っているのです。
もちろん私も貴方も、例外ではないのですが。
ああ、すみません。話がそれてしまいましたね。
私の母は子どもを流産して以来、気が触れてしまったのでしょう。他人の子どもを攫うようになりました。自分の子どもが死んだことが理解できなかったのかもしれません。子どもを探して辺りを徘徊し、幼い子どもを見つけては連れ帰っていました。もちろんほとんどは実母の元へ戻されましたが。しかし中には両親の元へ戻れず、彼女の元で過ごす子どももいました。
〝それが私なのです〟
ですから私は両親の顔も何もわかりません。出来損ないの人間なのです。私にとってこの組織は非常に居心地が良いものでした。欠陥だらけの人間でも、確かに生を実感できたからです。ですがそれも今日で終わりでしょうか。先ほど女の子とすれ違いました。彼女は幸せそうな子どもでした。私とは真逆なのでしょう。しかし彼女もまた単なる思い込みの中で過ごしているかもしれません。誰が誰の親かなんて、DNA鑑定でもしなければわからないでしょう。その遺伝子が誰のものか、知っているのは女だけです。しかし嘘を吐いてまでそれを偽るのなら、女とは浅ましい生き物ですね。
子どもとは可哀想な存在だと思いませんか。
女とは愚かな生き物だとは思いませんか。
貴方はどうですか。
貴方の母親は本当に貴方を生んだ女ですか。
母親さえ口を閉じてしまえば、腹の中身などわかりはしないのです。種をまくのは男ですが、どの種を育てるか選別するのは女です。
芽吹いたモノは、果たして本当に親のモノでしょうか。
「しかし貴女もまた女です。ならば、貴女も愚かなのでしょう。」
私が言うと彼女は僅かに微笑した。
突きつけられた銃口は喉を這い額に到達する。引き金にかけられた彼女の細い指はかすかに震えていた。
辺りに散らばった硝子の破片が月明かりに仄暗く輝いている。足元に見える街明かりは、漆の空間を極彩色に彩っていた。
「私を、殺すつもりですか」
「さあ、どうでしょう。ただこのままだといずれにしても警察が乗り込んできます。容易く捕まってやるつもりなのですか?」
「貴女の指と引き金次第でしょうね。彼らが見つけるのが私の死体かどうか。それだけです」
「まあ、諦めの早い」
額に感じる銃口の冷たさに目を細める。外界の縁に立ち、彼女は穏やかに笑んだ。
「他の団員は逃げました。幹部たちもおそらく。残っているのは貴女と私だけです」
「……」
「逃げるのならお逃げなさい。こうしている間にも、時間は経っています」
「優しいのですね。ですがだから貴方はダメなのです。何故そう易々と諦められるのです」
「それは貴女が言った通りだからですよ」
「……!」
「私が人型を得た肉塊に過ぎないからです」
彼女の瞳が見開き、虹彩が色を無くす。額から銃口が離れた。
――ダメだった。
私にはやはりダメだったのだ。
組織を再建するどころか再び破滅に導いた。あの方に声も届けられず、子ども一人に適わない。
呼吸を押し潰すようにのしかかる無力さに、思考がジワジワと焼かれていく。じっとりとした失望感が心臓を包み込んだ。
カチリと音が響く。彼女が拳銃を握りなおした。
「なら、一緒に死にましょう」
「……笑えない妄言ですね」
「ははっそんな不幸ぶった被害者の顔をして、今さらですよ」
「被害者、ですか」
「世の中滑稽な妄言に溢れているではありませんか。死にたがりは生きてて、生きたいと願う病人や老人は死んでいく。死にたいなら死ねばいいのです。誰も構っちゃくれはしません。死にたいくせに生きてるなんて惨めじゃありませんか。何故死にたいと願うのにまだ生きてるのです。なのに病人は生きる生きると喚いて簡単に死にます。皮肉な世界です」
「……」
「今まで加害者だった貴方が、私たちが、被害者のような顔をするのはそれと同じことではありませんか?」
「別にそのような思考は持ち合わせておりませんよ」
「罪は罪悪感を持って初めて裁かれるのです。今の貴方には、それはない」
「何故言い切ることができるのです」
「貴方の行動は統率者への憧憬からですから。貴方が抱く失望感は無力からでしょう。貴方はただ帰りを待ち望んでいただけで、悪事をしていた自覚がないのです。それでは法廷に立とうと、罰を受けようと、意味を成しません」
「……貴女には、罪悪感があると?」
「……」
彼女は拳銃を見詰める。唇は小さな弧を描いていた。遠くで、サイレンが聞こえる。
「さあ? 欠陥だらけの私はどうなのでしょうね」
「……」
「ただ今の貴方には罪を償う資格はありません。だから私は残ったのです」
「わかりませんね」
「人間はしょせん考えを持った肉塊です。その中に何かを発露させたいなら、外界からの刺激が必要なのです。……おそらく親という存在は、正しいものが発露するようにする役目を担うのでしょうね」
「……」
「誰が誰の子なんて誰にもわかりません。なら、女が望めばその瞬間それは子どもなのです」
「何を」
「ですから私は、貴方の母になろうと思うのです」
「!」
耳をつんざく銃声が空間を震わせた。
飛び散った赤い飛沫が頬に触れる。ごぼりと血泡を吐き出し、彼女は笑った。
「人間は二度生まれると遠い時代の哲学者は言いました。一度目は生きるために。二度目は愛するために」
「貴女は」
「ならば貴方を愛おしいと思った瞬間、私は二度目の誕生をしました。だから今度は」
「……!」
二度目の銃声が鳴り響いた。
「貴方が私を愛してください」
彼女の腹部から下は真っ赤に染まっていた。その体がゆっくりと傾く。真っ黒な世界に、赤い尾を引きながら彼女は沈んでいった。とっさに手を伸ばすが、血で滑って掴むことができない。
コガネのラジオ塔の展望台。そこから見渡せる街明かりの中に、まるで飛翔するようにそれは墜ちていく。赤を纏いながら彼女は至極穏やかに笑っていた。
私は二度目の誕生をした。
しかし二度目の母は私に罪悪感のみを与えて、夜の空へと消えていった。
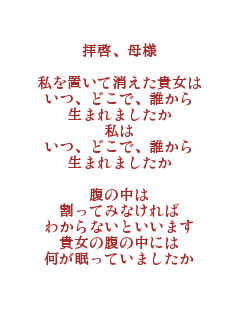
20101002